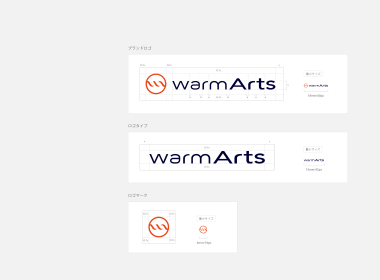見積もりが出せない。
ちょうど今から5年前、スリースノー事業部にはある課題がありました。元々、自社製品へのオーダーがあった時に対するレスポンスとして、3日以内に見積もりを提出することを決めていたのですが、3週間ほどを要することが常態化しており、時にはそれを上回ることも珍しくなかったのです。原因はどこにあったのでしょうか。
それは社内構造にありました。そもそも、事業部の構造はシンプルです。自社が開発した製品をカタログや展示会などでラインナップとして開示し、それを買い付けていただくお客様に販売しています。主なお客様は、地元の調理道具商社の方々です。ラインナップ内に欠品が生じている場合は、どのくらいで製造できるかを営業サイドと工場サイドが確認し、納期を確認後お客様へお見積もりとして提出するのです。

このシンプルな構造が機能不全に陥っていた時の状態は次のようなものです。工場サイドは、基本的にスリースノー専任というわけではありません。新越ワークス全体の案件に対応しており、中にはOEM製品も含まれます。受注を受けた順番に製造にあたっていました。したがって、製造リストのタイムスケジュールは生産品ごとに変わるばかりか、初めてのOEM製品が来れば通常よりも多くの時間を要します。ここに、自社製品といえども、新しい依頼が来ればリストの最後に加わるだけなため、自社製品にかかわらず納期が数ヶ月に及ぶことも十分にあり得るのです。
営業サイドからすれば、チームで扱っている品物以外の商材がどのような状態になっているのかを完璧に把握していません。お客様からみれば、新越ワークスの自社製品を製造するのに数ヶ月かかるというのは理解できないことです。したがって、工場と交渉していくことになるのですが、なかなか納期も短くならず返答ができない状態に陥ることになります。見積もりを提出できたとしても、お待たせした上で納期回答が3ヶ月となれば、失注につながりかねず、事業部としての信頼性に大きな影響が出ていました。
数字の洗い出し。
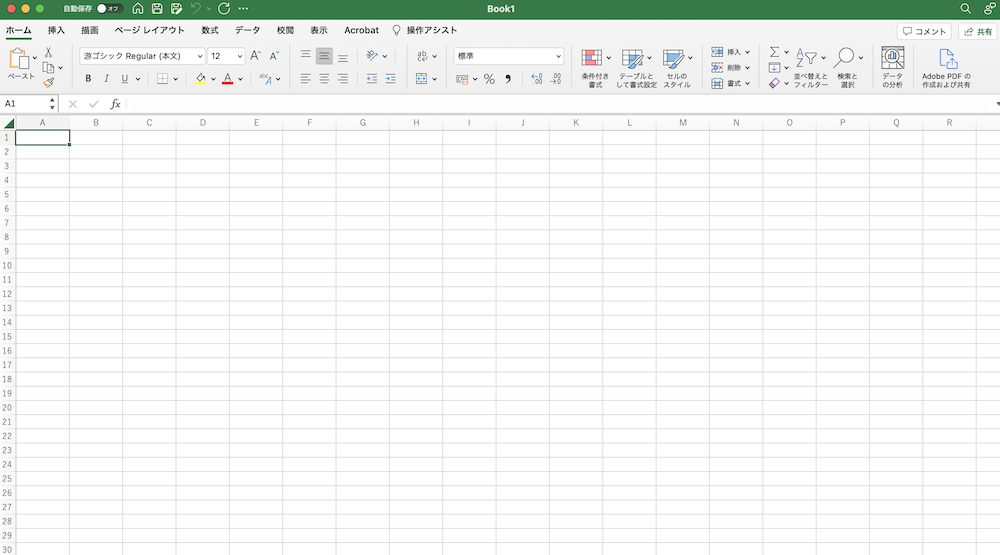
これらの状況を把握することも簡単ではありませんでした。在庫、発注、見積もりなど、事業部が保有しているすべての数字を洗い出し、どこに課題があるのかを洗い出していく作業に半年近くを要しています。その上で、上記の状態がまず把握できたというわけです。
解決していくためのプランニングにまとめるのには、そこからさらに3ヶ月ほどがかかりました。まず取り組んだのは、工場が生産している品物の数字を通年通して可視化しました。たとえば、1月には何をどのくらい作っていて、2月には何をどのくらい作っていて、といった具合です。次に、スリースノー製品に関して、通年通してどれがいつに売れているのかを可視化しました。3月にはどの発注が多くて、4月にはどの発注が多いのかという具合です。するとまず、スリースノー製品の通年を通して発注サイクルが見えてきました。Aという雑は5月が最も多くて、Bというざるは10月が最も多くなるという具合です。
次に、営業戦略を立てます。たとえば、売上を20%増やす目標を掲げる場合、作る製品を増やさなければなりません。それを、可視化された1年間の生産品の中に埋め込んでいくわけです。これは、Cという製品が最も売れる月の前後に、類似の製品を増やし、営業強化を行うといった具合です。
次に工場側の生産リソースを確認していきます。この時可視化した1年間の生産量には、大きな偏りがありました。理由は、発注が偏っているからです。そこで、仮に生産品を毎月均等にしてみて、それでも生産が溢れてしまうのかというリソース確認をしました。これには工場サイドに多大な協力をしてもらいました。すると、実はあらかじめ年間にわかっている生産スケジュールがあれば納期遅れが生じないほどリソースがあることがわかったのです。さらに、余力を作り出すことができることも確認できました。
アイデアの実行。
課題ははっきりしました。アイデアも自ずと決定します。要は、工場の年間生産スケジュールを、先に発注側が決定し、工場と協議した上で最終決定すればよいのです。手順はまず、各事業部が向上に発注する通年の営業戦略を作ります。これは、通年の売上目標ともリンクします。同時に、工場側は常に10%くらいの余力が残るように受注量を丁寧に検討します。理由は、突発的に生じるOEM品などがあるためです。この10%のリソースを超える品物はもう外注するというイメージでいるようにします。これで、営業と工場の準備が整いました。実行は全部を変えるのではなく、通年の計画を立てたのち1ヶ月ずつ実行していきました。そこで、実際の感覚とのズレがあれば微調整を加えていきます。半年ほど運用した段階で大きな問題はなく、運営が一気にスムーズになりました。これが、「見積もりが出せない」という問題が解決していった流れです。
このプロジェクトには余談があります。スリースノー事業部がその数年前より卸商社さんを集めて、1年に1回のBBQイベントを行うようになっていたのです。改善プロジェクトの総括と、イベントのアップデートを兼ねて、このイベントを新製品発表会、現状の事業報告会、そしてBBQイベントにし、ひとつ1年を通して事業部が頭にいれる日にしたのです。同時に、最初のアップデートの年に謝罪を行いました。上記のプロジェクトの報告と改善、そして今後への不安を払拭するように全力を上げるという報告を、各商社の前で行なったのです。このイベントへの反応は好意的なもので、以後、さまざまな課題はあるものの、事業部の構造が改善の兆しを見せています。