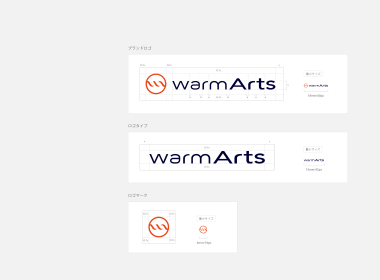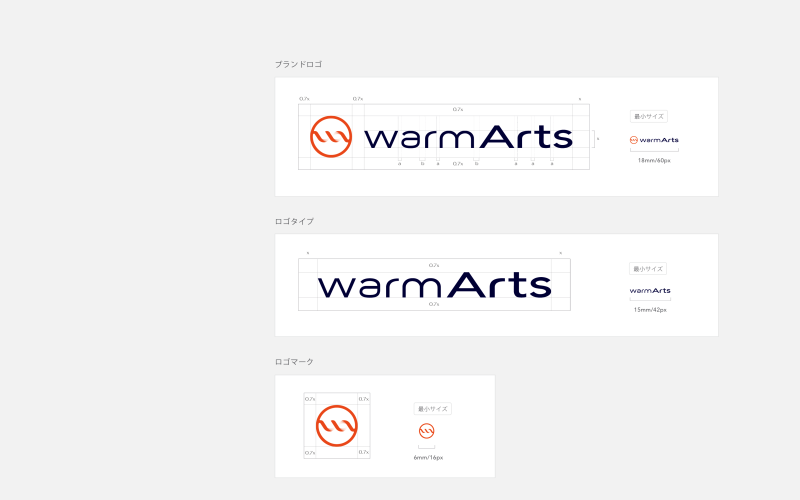製品開発とはなにか。
燕における製品開発は、どちらかと言えば過去から築き上げてきた方法論を繰り返していることが多く見られます。たとえば、何か形にする時には、工場の設備を使って、積み上げられた部材を目の前に、アイデアさえあればすぐに作ることができます。昔から積み上げられてきた製品も開発の痕跡もありますし、金属素材もあれば、豊富な設備もあります。
しかし燕には”なんでも作れる工場”はありません。各会社にある工場はそれぞれの製品や技術に特化した設備のみを有しているだけです。あくまで燕全体を見た時に「燕ならなんでも作れそうだ」となっているわけです。同時に、各会社の中にいる人材の多くは、社会的に見れば特定の分野におけるプロフェッショナルであり、もちろんその分野における数多くのアイデア、解決策を身につけていますが、社会的な問題解決のための豊富なアイデアを有しているわけでも多様で多彩な技術を有しているわけではありません。これは、まずしっかり理解すべきことだと思います。

料理に似ている。
特定分野における小さな課題解決はその分野のプロフェッショナルでなければ解決できないものですが、やっかいなことに、もっと大きな方法での課題解決は大体外からやってきます。たとえば、地図のプロフェッショナルは地図のアップデートには最高の能力を発揮しますが、Google MapのようなITソリューションを生み出すことはできませんでした。Googleは地図の会社ではありません。新越ワークスで言えば、ThreeSnowのザルの問題はザル作りのプロが解決できることですが、ザルを不要にするような調理の革新的な手法を生み出すことはおそらくできないということでもあります。では、麺のプロや、厨房機器のプロによって、ザルが不要になる技術が開発されたら我々はどうするのでしょう。
なくならないと考えることは簡単です。が、社会には常にニーズが存在します。困っていることだと言い換えてもいいですし、欲と言い換えてもいいです。このニーズを把握することは、技術を生かす上でとても大切です。家庭の料理で考えてみましょう。5人の家族がいるとします。高齢者が1名、壮年の夫婦が2名、小学生が2名です。今日、どんな夕食にしましょう。ここではまずニーズが必要です。どんなものを食べたらみんなが喜ぶか、です。家族のことなので、大体の好き嫌いは把握しています。日々の行動もわかっているので、先日みんなで話していたグラタンが今日はいいかもしれません。高齢者がいるので、その人には少し軽めのメニューも用意しましょう。
ここまで決まれば素材が決まります。そして次が技術です。たんたんといつものグラタンを作る方法もありますが、先日友人たちと食べたフレンチで出たグラタンの味はみんな好きそうです。ではそれを作りたい。となれば、今の自分の技術でいけるのか、調べなければならないのかがわかります。仮に時間もモチベーションも許すのであれば、その技術を調べ、チャレンジしてみるのも面白いかもしれません。少なくとも、これまでとは全く違った景色が見れるはずです。そもそも家族が美味しいといえるものになるかも不透明ですから、緊張感も段違いです。とはいえ、大体結局のところはできることで美味しいものを出す、ということに落ちつくことになります。なんだか、企業も似てますよね。
シミュレーションとエネルギー事業部。
新越ワークスのエネルギー事業部で、ユニークな試みが始まっています。燕に新たにできた、小規模データセンターを活用した開発シミュレーションの検証です。もともと、エネルギー事業部の開発は常にてさぐりでした。設計はすべて新越ワークス自社で行い、部材は外部から調達し組み上げ作業を実施してきました。設計時の部材検証もすべて手探り。文字通り、1から作り上げてきた体制と品質です。おおむねこれらはすべてうまく機能してきましたが、大きな問題にはつながらないものの難解な課題が生じつつもありました。代表的なのは排気口の課題です。
これまで、大体3万台のペレットストーブを販売してきました。このうち、年間1台〜2台ほどのストーブにおいて、外部環境の風圧などが極めて高い場合、排気がうまくいかず逆火が起きるケースがあるのです。クレームとしては極めて小さい数字なのですが、我々としては現在のように自然環境が目まぐるしく変化する時代においては極めて重要な課題だと捉えています。しかし、さまざまな検証を行なったものの原因特定に至るのは難しい。そこで、物理学的な専門知識を活用してシミュレーションを実施しながら、原因特定を行うための方法にトライしています。この中では、一次元的な分析というターンがあり、我々が構築した機器のそれぞれのパーツがどのように働いているのかを、数学的に解析するのです。こうしたプロセスを経ることで、我々がこれまで行なってきた分析が、いかに表面的であったのかを実感するとともに、完全に新しい地検によるユニークな製品開発ができうるという手応えも、まだまだ小さなものではありますが、確かに感じることができつつあります。
一方で、こうした専門知識がなければ製品開発ができないかといえばそうではありません。まず作ってみる。遊びながらでも組み上げてみる。この方が圧倒的に早く、ものになります。が、こうした時に専門知識の蓄積があるかないかは、品質にも、特許にも、イノベーションにもつながることがわかってきました。さて、私たちは今後、どのようにユニークな商品やサービスが作っていけるのか。新しい挑戦が始まっています。